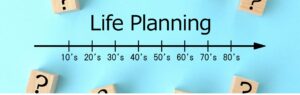「若者を搾取して高齢者を守る国」──社会保険制度の逆転現象
日本の社会保障制度は、もはや“支える人”より“支えられる人”の方が多い。 その現実に、私たちはどこまで目を向けているだろうか。
Table of Contents
社会保険料の値上げ──それは誰のため?

毎年のように上がる社会保険料。給与明細を見るたびにため息をつく人も多いはず。 しかし、その負担は本当に「未来の安心」のためなのか。 実際には、増え続ける高齢者の医療費・年金支給額を賄うための“延命策”に過ぎないのではないか。
データが語る“逆転現象”

- 社会保険料率は過去20年で約1.5倍に上昇
- 若年層の可処分所得は減少傾向
- 高齢者の医療費は年間40兆円を超え、今後も増加予測
この構造は、まるで「若者が高齢者を支えるために犠牲になる」ような仕組みに見える。 しかも、少子化が進む中で、その“支える人”は年々減っている。
他国はどうしているのか?
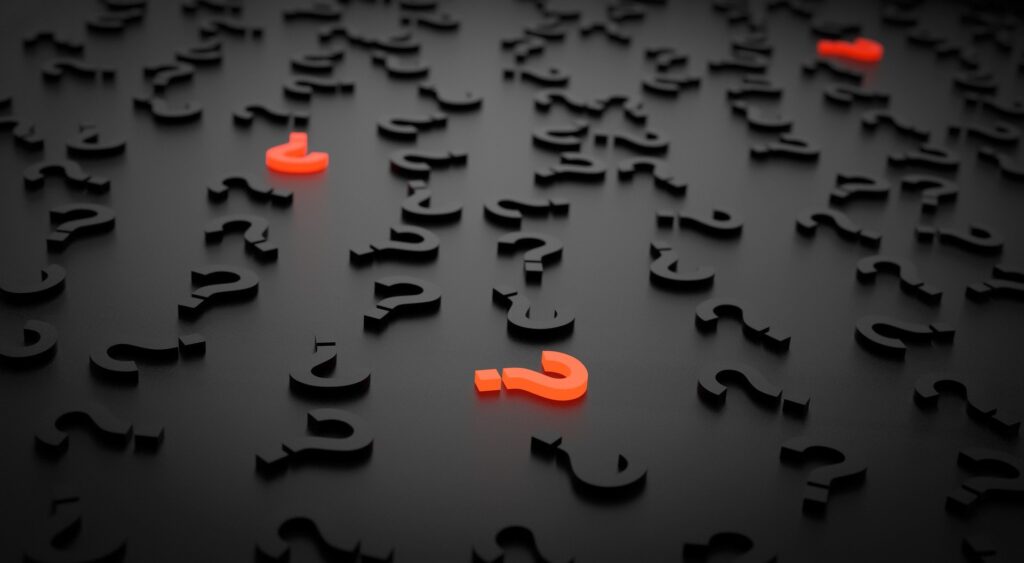
スウェーデンでは、所得比例の保険料制度により公平性を確保。 ドイツでは高齢者の就労支援が進み、社会参加が促されている。 シンガポールは自己責任型の貯蓄制度で、国家の財政負担を抑えている。
一方、日本は一律の負担と年齢による優遇が続き、若年層へのしわ寄せが顕著だ。
本末転倒の構造
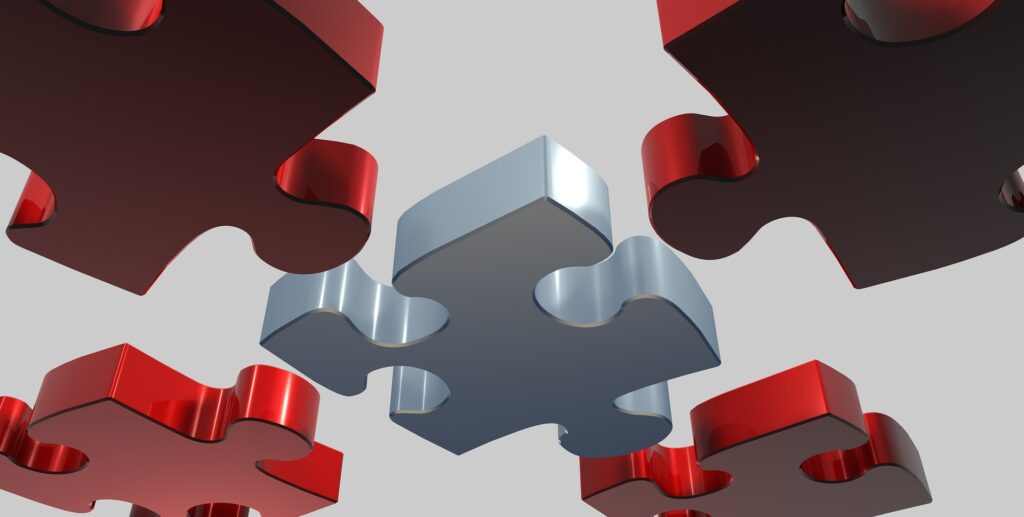
制度の目的は「全世代の安心」のはず。 しかし今の仕組みでは、若者の生活を圧迫し、将来の支え手を減らす方向に進んでいる。 これはまさに本末転倒。守るべきは“制度”ではなく、“人”ではないか。
では、どうすればいいのか?

- 所得・資産に応じた負担の再設計
- 高齢者の社会参加を促す制度改革
- 医療・介護の効率化と予防重視への転換
- 若年層への支援強化(教育・子育て・住宅)
結論──制度疲弊の先にある“選択”
社会保障制度は、誰かの犠牲の上に成り立つべきではない。 今こそ、値上げという“延命策”ではなく、構造改革という“治療”が必要だ。 未来を支える世代が希望を持てる社会へ──その選択を、私たちは迫られている。