相続対策の落とし穴!小規模宅地の特例は“実態ある同居”がカギです ~葛飾区で実際にあった“小規模宅地の特例”否認事例から学ぶ~
Table of Contents
はじめに
「親と同居していれば、小規模宅地の特例は使えるはず」——そう思っていた方が、実は税務署から“否認”の通知を受けたという相談が、葛飾区でありました。 地域密着型FPとして活動する中で、こうした“誤解”に触れる機会が増えています。今回は、実際にあった事例をもとに、制度の落とし穴と対策についてお話しします。
※過去の参考記事はこちら
実際の相談事例(仮名)

葛飾区在住のAさん(50代・会社員)は、数年前から親の介護を理由に住民票を親の家に移していました。 「これで特例は使える」と安心していたそうですが、実際の生活は週末だけ親の家に通い、平日は自宅マンションで過ごす日々。
相続が発生し、申告の際に特例を適用しようとしたところ—— 税務署から「実態のない同居」として否認されてしまいました。
なぜ否認されたのか?
税務署が重視するのは「住民票」ではなく、生活の実態です。 具体的には、以下のような点がチェックされます:
- 郵便物の送付先がどこか
- 水道光熱費の支払い名義
- 家財道具がどこにあるか
- 通勤経路や生活時間帯の記録
「介護目的で一時的に通っていた」だけでは、“社会通念上の同居”とは認められないこともあるのです。
地域密着FPとしての気づき
葛飾区では、親の家が商店街の近くにあるケースも多く、生活拠点が分かれがちです。 「親の家に通っている=同居」と思い込んでしまう方も多く、制度の誤解が広がっている印象です。 地域の事情を踏まえたアドバイスが必要だと、改めて感じました。
どう備えるべきか?
生活の実態を記録することが大切です。以下に幾つか例を挙げてみました。
- 郵便物の送付先を親の家に変更
- 水道光熱費の支払い名義を自分に
- 家財道具の搬入記録や写真を残す
- 通勤経路を親の家からにする
- 相続発生前から、FPや税理士に相談しておく
あなたの同居、実態あり?
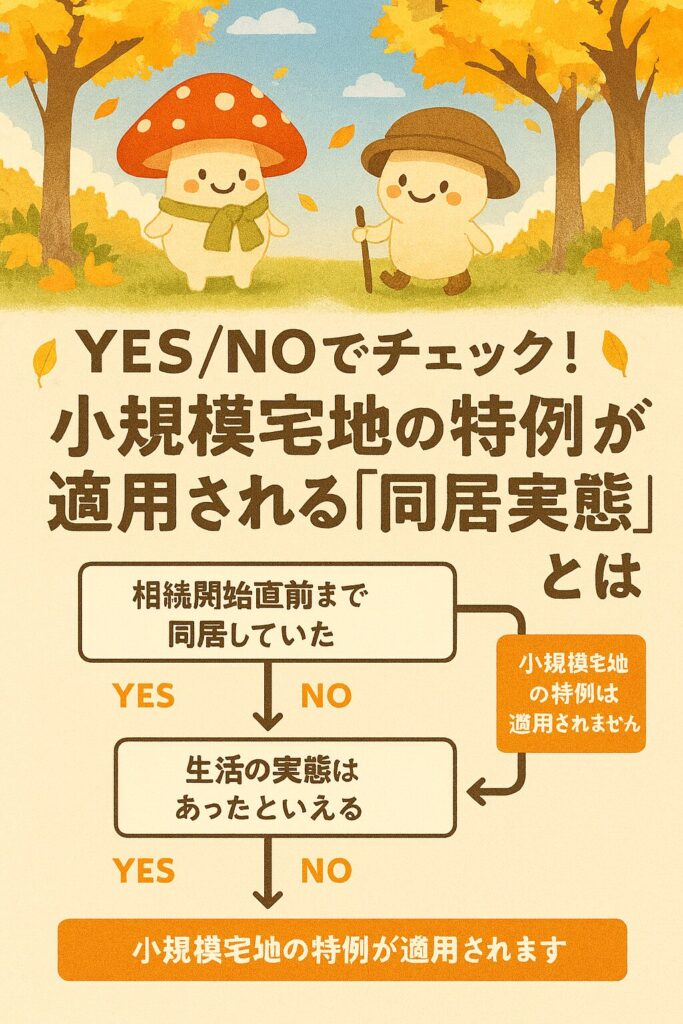
まとめ
「同居していれば安心」——そんな思い込みが、思わぬ落とし穴になることもあります。 でも、ちょっとした気づきと準備で、大切なご家族の住まいを守ることができるんです。
葛飾区の事例を通して、私自身も“実態のある暮らし”の大切さを改めて感じました。 地域の皆さんが安心して相続を迎えられるよう、これからも身近な視点で情報を届けていきたいと思います。
もし気になることがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。 一緒に、無理なく備えていきましょう。

