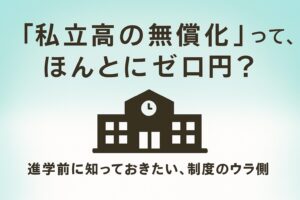ケアマネ更新制度の廃止──それは“負担軽減”なのか、“制度の再生”なのか
2025年、厚生労働省はケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制度を廃止する方針を打ち出した。 これまで5年ごとに義務づけられていた更新研修は、今後は任意の研修へと移行し、オンデマンド化や分割受講など、柔軟な学びの形が導入されるという。
表向きの目的は「負担軽減」。 確かに、時間的・経済的な負担は軽くなるかもしれない。 でも、そもそもこの制度変更は何のために行われるのか? そして、これによって何が解決されるのか?
ケアマネジャーの担う役割は、制度の“調整役”にとどまらず、利用者の人生に寄り添う“伴走者”でもある。 その重みを支える制度であるべきなのに、今回の見直しは「根本的な課題」に触れていないようにも見える。
Table of Contents
🧱処遇の低さと業務の重さ──“感情労働”の見えづらさ
ケアマネジャーは、利用者・家族・事業所・行政との間をつなぐ、まさに介護のハブ。 その業務は多岐にわたり、調整力だけでなく、共感力や忍耐力も求められる。 それにもかかわらず、報酬や待遇は十分とは言えず、「感情労働」としての負荷が見えづらいまま放置されている。
更新制度の廃止は、研修の負担を軽くするかもしれない。 でも、日々の業務そのものの重さには、何の変化ももたらさない。
🌱若手の参入障壁──“なりたい”と思える制度へ
ケアマネ資格の取得には、実務経験が必要で、道のりは決して短くない。 さらに、更新研修の負担が重いと、若い世代が「なりたい」と思いにくい。 制度の持続可能性を考えるなら、キャリアパスの明確化や魅力的な支援体制が必要だ。
更新制度の廃止は、入口のハードルを少し下げるかもしれない。 でも、その先にある未来像が描けなければ、若手の定着にはつながらない。
🏞地域差と孤立感──“つながり”の再構築を
都市部と地方では、業務量や支援体制に大きな差がある。 孤立しがちなケアマネも多く、情報共有や相談の場が不足している。 制度の見直しと同時に、横のつながりを育てる仕組みが求められている。
更新制度の廃止は、形式的な研修からの解放かもしれない。 でも、現場の孤独を癒すものではない。
🌀制度の柔軟性──“創意工夫”を活かせる土壌へ
制度が画一的すぎて、現場の創意工夫が活かしづらい。 利用者一人ひとりに寄り添うには、ケアマネ自身が柔軟に動ける余地が必要だ。 更新制度の見直しは、学びの形を柔軟にする一歩かもしれない。 でも、制度全体が柔軟でなければ、現場の工夫は根づかない。
“制度の再生”は、現場の声から始まる
更新制度の廃止は、確かに一つの転機かもしれない。 でも、それだけでは足りない。 ケアマネジャーが安心して働ける環境、若手が希望を持てる制度、地域で支え合える仕組み── それらを育てるためには、現場の声に耳を傾けることが何よりも大切だ。
制度の根っこを見直すこと。 それが、本当の“負担軽減”につながるのではないだろうか。
過去の関連記事はこちらでご紹介いたします。